ランニングシューズを普段履きにしている人を街中でよく見かけますが、本当にそれは正しい選択なのでしょうか。多くの人が「ランニングシューズを普段履きにするのは良くない?」と疑問を抱えており、特に「ランニングシューズでウォーキングしてもいいですか?」という声もよく耳にします。
この記事では、ランニングシューズを日常で使う際に気を付けたいポイントを中心に、「厚底シューズはよくない理由は何ですか?」や「普通のスニーカーとの違いは何ですか?」といった具体的な疑問にも触れていきます。また、「普段履き ナイキ」などブランド別の選び方、「普段履きの寿命」に関する注意点もわかりやすく解説します。
さらに、「普段履きのおすすめ」モデルの紹介や、「普段履きをおしゃれ」に見せるコーディネートのコツもご紹介。「ウォーキングシューズの普段履き」との比較や、「ランニングシューズ は疲れる」と感じる理由など、実際に起こり得るデメリットを総合的に整理しています。
ランニングシューズを普段使いにする前に、ぜひ本記事を参考にして、足元から健康で快適な生活を考えてみてください。
- ランニングシューズが日常使用に適さない理由
- 普段履きによるシューズの寿命や機能低下のリスク
- ウォーキングや立ち仕事での疲れやすさの原因
- 普通のスニーカーやウォーキングシューズとの違い
ランニングシューズ普段履きのデメリットとは?

- 普段履きにするのは良くない?
- ウォーキングしてもいいですか?
- 厚底シューズはよくない理由は何ですか?
- 普通のスニーカーの違いは何ですか?
- 疲れると感じる理由
普段履きにするのは良くない?

ランニングシューズは、その名の通りランニングという特定の運動をサポートすることを目的として設計されています。前方向への推進力を高める構造や、着地時の衝撃を吸収するクッション性、軽量性など、速く走るために必要な要素を重視して作られているのが特徴です。
ただし、このような構造は、普段の歩行や長時間の立ち仕事といった日常動作には必ずしも適していません。ランニングと歩行では足の着地位置や重心の移動、筋肉の使い方に違いがあり、ランニングシューズがそのまま普段使いに適合するとは限らないのです。
特に競技用シューズにおいては、軽量化とパフォーマンス向上を最優先として設計されているため、耐久性や足元の安定性が犠牲になっていることもあります。ソールが薄かったり、かかとのクッションが不十分なことが原因で、長時間履いた際に足への負担を感じやすくなり、歩行が不安定になったり疲れやすかったりすることもあります。
また、素材の選定も問題になります。競技用のモデルは通気性を確保するためにメッシュ素材などが使用されており、これが破れやすく、普段の着脱や街中での使用には耐えられないケースも見受けられます。
このため、ランニングシューズを普段履きにする場合には、見た目やブランドだけでなく、実際の使用シーンに適しているかをしっかりと見極めることが大切です。競技用ではなく、タウンユースを前提に設計されたクッション性やサポート性に優れたモデルを選ぶことで、歩行時の快適性や安全性を確保することができます。
ウォーキングしてもいいですか?

ウォーキングとランニングでは、見た目は似たような動きに見えても、実際には足の使い方や着地のパターン、体重移動の仕方が大きく異なります。ウォーキングは「ヒール・トゥ」と呼ばれる、かかとからつま先へと重心を移動させる動作が基本です。一方、ランニングでは「フォアフット」または「ミッドフット」といった、つま先や前足部で着地するスタイルが一般的です。
多くのランニングシューズは、こうした前足部の着地をサポートするように設計されています。その結果、ウォーキングのようにかかとから着地する動作には対応しきれず、歩行時に違和感を覚える原因になるのです。かかとのクッション性が不十分だったり、ソールが湾曲している構造がかえってバランスを崩しやすくする場合もあります。
また、ウォーキングでは足を長時間使い続けることが多く、シューズの安定性やアーチサポートの有無が非常に重要になります。ランニングシューズは走るために軽さと反発力を重視しているため、足をしっかりと支える設計ではないモデルも多く存在します。そのため、長時間のウォーキングでは足裏の疲れ、足首や膝への負担を感じやすくなる傾向があります。
さらに、ウォーキング用のシューズには滑りにくいアウトソールや、安定性を高めるかかと部分の構造など、歩行に特化した機能が備わっていることが一般的です。こうした機能が欠けているランニングシューズでは、坂道や段差のある場所などで不安定になりやすく、安全性にも影響を及ぼす可能性があります。
ウォーキングを習慣にしている方や、日常的に長距離を歩く機会が多い方には、やはり専用のウォーキングシューズを選ぶことをおすすめします。これにより、身体全体への負担を軽減し、快適で安全な歩行を維持することができます。
厚底シューズはよくない理由は何ですか?

厚底シューズは、クッション性に優れ、着地の衝撃を吸収しやすいため、特に長距離ランナーや関節への負担を軽減したい人にとっては大きなメリットがあります。ソールが厚いため、足へのダメージを抑えながら快適に走ることができるという点では、非常に魅力的な選択肢です。
しかし、その厚みは日常生活において必ずしも利点とは限りません。まず、厚底であることで地面との距離が遠くなり、足裏の感覚が鈍くなりやすいという欠点があります。足元の凹凸を感じ取りづらくなり、小さな段差や石、マンホールのフチなどに気付きにくくなるため、つまずきや転倒のリスクが高まるのです。特に舗装が不安定な路面では慎重な歩行が求められるでしょう。
また、ソールが厚くなることで重心が高くなり、身体のバランスが不安定になることもあります。これは足首の可動域に影響を与え、結果として足首の捻挫やふくらはぎへの過剰な負荷を引き起こす可能性があります。
さらに、厚底シューズはソールが硬めに設計されていることが多く、自然な足の曲がりや歩きのリズムが制限されることがあります。これによって、歩行時に不自然な動作を強いられたり、無意識のうちに姿勢が崩れたりするケースもあります。長時間の使用で腰や膝、肩などに負担がかかるといった二次的な問題にもつながりかねません。
見た目についても、厚底シューズはボリューム感のあるデザインが多く、服装とのバランスをとるのが難しいこともあります。ファッション性を重視する場合には、スタイリングとの相性を考慮する必要が出てくるでしょう。
このように、厚底シューズには確かに優れた点もありますが、用途やシーンによってはその特徴がデメリットになりうることもあります。特に普段履きとして選ぶ場合には、歩きやすさ、安定性、見た目のバランスなどをトータルで考えて判断することが大切です。
普通のスニーカーとの違いは何ですか?

ランニングシューズと普通のスニーカーには、目的や設計思想に明確な違いがあります。ランニングシューズは、速く走ることを前提に作られており、前方への推進力を高めるための構造が採用されています。具体的には、軽量で反発力の高いミッドソール、通気性に優れたアッパー素材、滑りにくく柔軟性のあるアウトソールなどが特徴です。これにより、ランニング時のパフォーマンス向上や怪我のリスク軽減が期待できます。
しかし、こうした設計は歩行や日常の使用には必ずしも適していないことがあります。ランニングシューズは、前足部での着地や高頻度の反復運動を想定しているため、かかとから着地する通常の歩き方ではクッションや支えが不十分に感じられる場合もあります。また、耐久性についても、使用頻度や環境によっては摩耗が早く進行する傾向があります。
一方、普通のスニーカーは、日常生活での快適性と安定性を重視して設計されています。アウトソールはフラットでグリップ力に優れ、アッパー素材には合成皮革やキャンバスなどの耐久性のある素材が使用されることが多く、ラフな使用にも耐えやすいのが特徴です。また、足を包み込むようなフィット感や、着脱のしやすさ、さらにはデザイン性にも優れており、ファッションアイテムとしての役割も果たしています。
たとえば、街歩きやショッピング、通勤通学など、長時間歩いたり立ち続けたりするシーンでは、足への負担を軽減し、疲れにくくするためのクッション性と安定感が重要です。その点で、普通のスニーカーは多様なシーンに適応できる万能な靴といえます。
使用目的に応じて靴を選ぶことで、足の健康を守りつつ快適な毎日を送ることができます。見た目だけで判断せず、機能性や用途に合ったものを選ぶように心がけましょう。
疲れると感じる理由

日常生活でランニングシューズを履くと、思ったよりも足が疲れたと感じることがあります。これは一見不思議に思えるかもしれませんが、靴の構造が日常の歩行に最適化されていないために起こる現象です。
ランニングシューズは基本的に、走ることに特化して設計されており、推進力を高めるために重心がやや前方に移動しやすい構造となっています。加えて、つま先がわずかに上がった「ロッカー構造」や、ミッドソールに高い反発力を持たせた設計が多く採用されています。これらの設計は、走行中の効率を上げる一方で、歩行時には自然な足運びを妨げ、知らず知らずのうちに筋肉に無理をさせてしまうことがあるのです。
特に長時間歩いたり立ち仕事が続いたりすると、ふくらはぎやアキレス腱、さらには腰回りの筋肉までに負担が広がり、疲れやすさを感じる原因となります。また、ランニングシューズは軽さや通気性を重視していることから、足を包み込むホールド感が弱いモデルもあり、そのことも安定感を欠く要因となります。
さらに、シューズのクッション性が高すぎると、足裏の感覚が鈍くなり、必要以上に足底の筋肉を使ってバランスを取ろうとするため、かえって疲労が蓄積しやすくなることもあります。特にアーチサポートが不足していると、偏平足気味の人にとってはさらに疲れやすさを感じることが多いでしょう。
このように、見た目には快適そうなランニングシューズでも、歩行や立ち仕事といった日常生活においては、必ずしも適しているとは限らないのです。
普段の生活で疲れにくく、かつ安定して歩ける靴を探している場合は、カジュアル用途に設計されたスニーカーや、歩行動作を前提に作られたウォーキングシューズを選ぶことをおすすめします。これらは歩行時の衝撃を適度に吸収し、足をしっかり支える設計が施されているため、より自然な歩き方ができ、疲れを感じにくくなります。
ランニングシューズ普段履きの注意点と対策

- ナイキは普段履きに向いているのか
- 寿命はどうなる?
- おすすめモデルはある?
- おしゃれに履きこなすコツ
- ウォーキングシューズとの違い
- ランニング用と日常用を分けるべき理由
ナイキは普段履きに向いている?

ナイキのランニングシューズは、スタイリッシュなデザインと高い機能性を兼ね備えており、普段履きとしても注目されるブランドです。特に若年層を中心にファッションアイテムとしても人気があり、街中でナイキのシューズを履いている人をよく見かけます。
ただし、ナイキの全てのランニングシューズが普段履きに適しているとは限りません。たとえば、「ヴェイパーフライ」や「ズームフライ」などの競技志向の強いモデルは、軽量でクッション性に特化している反面、耐久性や安定感が日常使用にはやや不足している場合があります。
特に、かかと部分のソールが薄く、地面との接地面が少ないため、歩行中にバランスを崩しやすくなることもあります。また、アウトソールのラバーが小さく配置されているタイプは、アスファルトなど硬い路面での使用によって短期間で摩耗してしまう可能性があるため、注意が必要です。
一方で、ナイキの中でも「エア ズーム ペガサス」シリーズのようなクッション性、耐久性、安定感のバランスがとれたモデルは、日常生活でも安心して使える設計になっています。このモデルは長年にわたって愛用者が多く、初心者ランナーから日常使いのユーザーまで幅広く支持されています。
さらに、ナイキの「リアクト インフィニティ」や「レボリューション」シリーズも、ウォーキングや通勤など軽い運動と普段履きの両方に対応できる優れたモデルです。デザインも洗練されているため、カジュアルな服装との相性も良く、汎用性が高い点も評価できます。
このように、ナイキのランニングシューズはモデルによって特性が大きく異なります。普段履きを目的とする場合は、見た目だけで判断するのではなく、シューズの構造や設計思想を理解した上で、自分の用途やライフスタイルに合ったモデルを選ぶことが大切です。
寿命はどうなる?

ランニングシューズは使用時間と使用環境に大きく影響を受けるアイテムであり、使い方次第で寿命は大きく変動します。特にソールのクッション性やミッドソールの反発力は、時間の経過とともに劣化していく消耗部品であり、使用頻度が高ければ高いほどその劣化も早まります。
普段履きとして毎日使用すると、シューズは走るときよりも長い時間足に接していることが多く、歩行中の摩擦や圧力によりソールが平たくつぶれていく速度が速くなります。結果として、数ヶ月も経たないうちに弾力性が失われ、歩いていても衝撃を吸収してくれなくなることがあります。
例えば、週3回程度のランニングであれば半年から1年程度は持つシューズも、通勤や買い物などで1日何時間も履いていれば、3~4ヶ月ほどでソールがすり減り、アッパー部分にほつれが出てくるケースも少なくありません。さらに、普段履きでよくあるのが、頻繁な脱ぎ履きによってかかと部分が潰れてしまったり、内側のインソールがズレて快適性が損なわれてしまう点です。
このような状況では、いざランニングで使用しようとした際にクッション性やサポート力が落ちており、足を痛めたり怪我をするリスクも高くなります。また、シューズが本来の性能を発揮できなくなることで、走行パフォーマンスの低下やフォームの乱れを引き起こす可能性もあります。
このため、シューズの寿命を最大限に保つためには、目的に応じて使用を分けることが非常に重要です。ランニング専用、普段用と用途をしっかり区別し、それぞれの目的に合ったシューズを履き分けることで、機能性を長く維持することができます。シューズを清潔に保つことや、使用後は風通しの良い場所で乾かすといったケアも、寿命を延ばすポイントのひとつです。
おすすめモデルはある?

普段履きに適したランニングシューズを選ぶ際には、クッション性、耐久性、安定感、そしてデザイン性のバランスがとれたモデルを選ぶことが大切です。走るための機能を備えつつ、日常の歩行にも無理なく適応できることが重要なポイントです。
代表的なモデルとしてまず挙げられるのが、BROOKS(ブルックス)の「ゴースト」シリーズです。ゴーストは本来ランニング用途に設計されたモデルですが、柔らかく反発性のあるクッションと、ブレを抑える構造によって、普段の歩行でも快適さを実感できます。特に「ゴースト15」は価格と性能のバランスが非常に良く、通勤や散歩など日常のあらゆるシーンで活躍します。
次に、ナイキの「エア ズーム ペガサス」シリーズもおすすめです。ペガサスはナイキの中でも定番中の定番で、ランニング初心者からベテランまで幅広く支持されているモデルです。クッション性と安定性が高く、足への負担が少ないため、長時間の歩行でも疲れにくい設計となっています。また、スタイリッシュなデザインはどんな服装にも合わせやすく、普段履きにもぴったりです。
他にも、HOKA ONE ONE(ホカオネオネ)の「クリフトン」シリーズは、独自の厚底クッションによって抜群の柔らかさと安定感を実現しています。衝撃をしっかり吸収しつつ軽量なため、街歩きや旅行にも最適です。
さらに、ASICS(アシックス)の「ゲルカヤノ」シリーズも視野に入れると良いでしょう。サポート力が強く、足全体をしっかり支える構造のため、オーバープロネーション(足の内側に傾きやすい人)にも対応可能です。こちらも、ランニング用としてはもちろん、普段のウォーキングにも非常に安定感があります。
これらのモデルは、いずれもランニング専門ブランドが推奨する信頼性の高いシリーズであり、日常使いでも快適さと機能性を両立できます。自分の足の形状や歩き方、使用するシーンに合わせて選べば、失敗することはほとんどありません。
おしゃれに履きこなすコツ

スポーツアイテムとしての印象が強いランニングシューズですが、最近ではファッションアイテムとしての地位も高まりつつあります。選び方とコーディネートの工夫によって、普段のスタイルに自然に溶け込ませることが可能です。
まず意識したいのは「カラーの統一感」です。たとえば、全体のトーンをモノトーンやベージュ系でまとめることで、ランニングシューズの存在感を適度に抑えつつ、上品な雰囲気を演出できます。服装がシンプルなときには、あえて靴だけビビッドなカラーを選び、差し色として使うのも効果的です。これにより、足元がアクセントになり、シンプルなコーディネートに個性が加わります。
次におすすめなのが「靴ひもを変える」テクニックです。靴ひもを同系色でトーンを合わせると上品に見せられますし、反対にあえて異なる色にして遊び心を加えることもできます。リバーシブルの靴ひもや柄入りのデザインを選ぶと、さらに幅広いアレンジが楽しめます。
また、「パンツの丈」と「靴のボリューム」のバランスも大切です。厚底タイプのランニングシューズであれば、やや短めのパンツを合わせると全体のシルエットが引き締まり、スタイルアップして見える効果があります。
最後に、スポーツミックススタイルを意識すると、おしゃれにまとまりやすくなります。例えば、テーラードジャケットにスウェットパンツ+ランニングシューズといった組み合わせは、カジュアルさときちんと感を両立できるため、大人の普段使いに適しています。
このように、少しの工夫でランニングシューズも十分におしゃれアイテムとして活用できます。機能性とファッション性を両立させるためにも、色味・素材・バランスを意識してコーディネートすることがポイントです。
ウォーキングシューズとの違い

ウォーキングシューズは、歩行という日常的な動作に最適化された構造を持っています。そのため、クッション性と安定性のバランスが非常に優れており、足裏への衝撃を効率よく吸収しながら、足全体の負担を和らげてくれる設計になっています。特に、歩幅や着地時の力の分散を考慮したソール設計や、アーチサポートによって、足の形状に沿って自然にフィットする構造になっていることが特徴です。
一方で、ランニングシューズは、前方への動きをサポートするように作られており、着地から蹴り出しまでのスピードを意識した構造が採用されています。そのため、走行時の効率は高いものの、長時間の歩行では筋肉の使い方に違和感が生じたり、安定感に欠けたりすることがあります。また、軽量化や反発力を優先することで、足元のサポート力が十分ではないモデルも存在します。
さらに、ウォーキングシューズは長時間歩くことを前提としているため、滑りにくいアウトソールや、通気性の高い素材、足首のサポートを考慮したカット設計などが取り入れられています。これにより、通勤や外回り、買い物などの多様なシーンで安心して使用することができます。
普段の通勤や散歩といった日常生活で歩く時間が長い人にとっては、ウォーキングシューズの方が断然快適に感じられるでしょう。見た目はやや地味なものもありますが、最近ではファッション性も高く、シンプルでどんなスタイルにも合わせやすいデザインが増えています。
総合的に見ると、歩くことを主目的とする人には、ウォーキングシューズを選ぶことで足への負担を軽減し、長時間の歩行でも疲れにくい快適な毎日をサポートしてくれます。
ランニング用と日常用を分けるべき理由

ランニングシューズを日常用として兼用すると、ソールの摩耗やクッション性の低下が予想以上に早く進行してしまいます。特に、毎日履くような使用頻度の高い場面では、靴底の接地部分がすり減りやすく、元々設計されていた反発力や衝撃吸収機能が徐々に損なわれていきます。その結果、肝心なランニング時に必要なパフォーマンスが発揮できなくなり、フォームの乱れやケガのリスクも高まる恐れがあります。
さらに、走る動作と歩く動作では、足の接地方法や筋肉の使い方、重心移動の仕方が異なります。走行中は前足部での着地が多く、蹴り出しも強いため、クッションの配置や靴の反発性が重要になります。一方で、歩行はかかとからの接地が基本で、重心も緩やかに移動します。これにより、ランニングに特化した構造の靴を歩行に使うと、違和感や疲労の原因になることがあります。
そのため、使用目的に応じたシューズを揃えることは非常に重要です。ランニング用はランニングに、日常用は日常の歩行や通勤にと、それぞれの役割に合わせて履き分けることで、足や膝、腰への負担を減らすことができます。また、専用の靴を使い分けることにより、1足あたりの使用時間が分散されるため、結果的にシューズ全体の寿命を延ばす効果もあります。
加えて、使い分けによってシューズのメンテナンスもしやすくなり、汗や湿気による劣化を防ぎやすくなるというメリットもあります。足元の快適性や安全性を長く保つためにも、シーンに応じたシューズの選択は欠かせません。
ランニングシューズを普段履きにするデメリットまとめ
- 歩行動作に最適化されていない構造で違和感が生じやすい
- 前足部着地向け設計がかかと着地の歩行に合わない
- ソールが薄いモデルは足への衝撃が大きい
- 長時間歩くとクッション性が不足し疲れやすくなる
- 素材が繊細で街歩きの摩耗に弱い
- 厚底による重心の不安定さで転倒リスクが上がる
- 靴底がすり減りやすく寿命が短くなりがち
- 普通のスニーカーに比べて耐久性が低い傾向がある
- 反発力重視の構造が自然な足運びを妨げる
- クッションが柔らかすぎて足裏の感覚が鈍くなる
- アーチサポートが不足し偏平足には不向き
- 滑りにくさや安定感が不足し安全性に欠ける場合がある
- 普段履き用途には価格帯が高めでコスパが悪い
- ファッション性を重視するとモデル選びが難しい
- ランニング用と併用すると機能が劣化しやすい
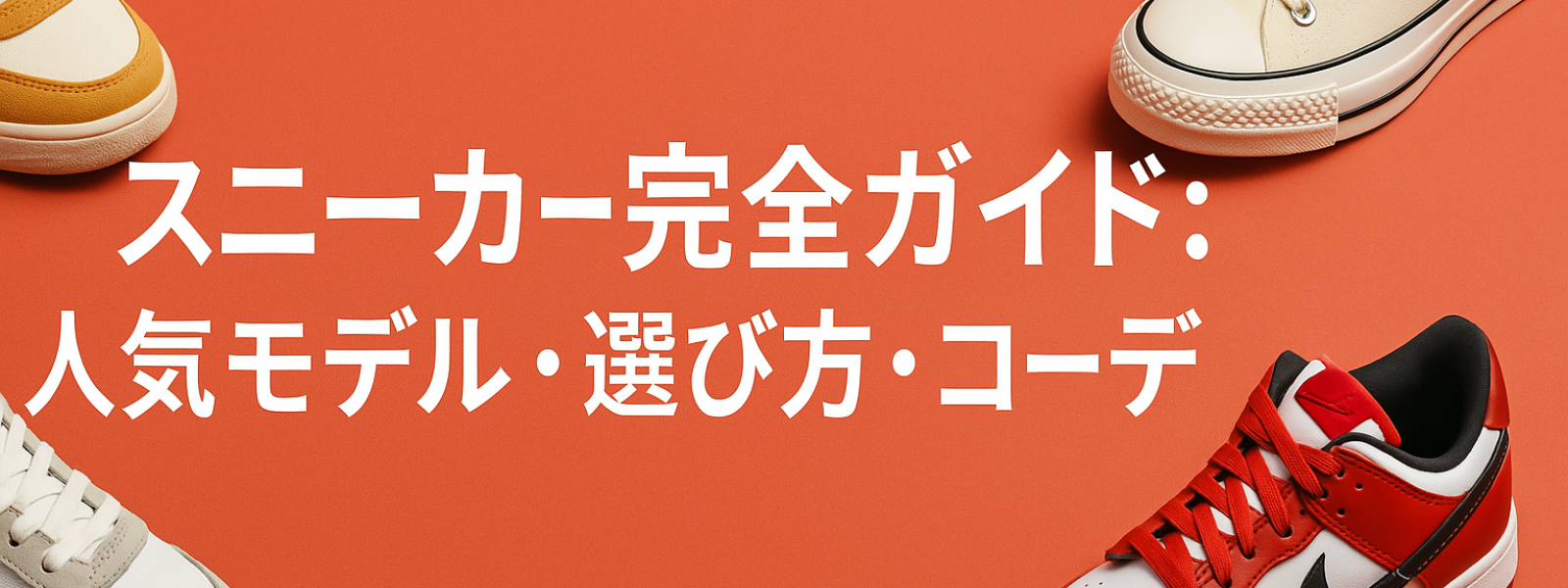

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e60755.13b58b60.46e60756.a185d51e/?me_id=1207922&item_id=10440187&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Falpen%2Fcabinet%2F250404%2F1_4%2F4320567213_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e60c1a.d65d33f4.46e60c1b.d92c86f5/?me_id=1210102&item_id=10447922&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyakyu-kasukawa%2Fcabinet%2Fyy%2Fglx7falcon5_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e61659.6a013b0b.46e6165a.49caca5c/?me_id=1350316&item_id=10006682&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fas-stock%2Fcabinet%2Fmem_item%2F06610495%2F10813289%2Fdv4129-001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e6191f.9fc1d394.46e61920.d61f89d5/?me_id=1378132&item_id=10037147&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffutabasp%2Fcabinet%2Fimage91%2Fdm8974-300-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e60755.13b58b60.46e60756.a185d51e/?me_id=1207922&item_id=10447518&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Falpen%2Fcabinet%2F250404%2F1_4%2F4303567433_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e60755.13b58b60.46e60756.a185d51e/?me_id=1207922&item_id=10440887&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Falpen%2Fcabinet%2Fimg%2F640%2F4304567013_9.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e60755.13b58b60.46e60756.a185d51e/?me_id=1207922&item_id=10440181&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Falpen%2Fcabinet%2F250404%2F1_4%2F4303567513_8.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e62921.d767bc9f.46e62922.ded9a904/?me_id=1195055&item_id=10186558&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsportsmario2%2Fcabinet%2Fevidence_20250330%2Fd08hok1110534bw_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e63195.5d6071be.46e63197.b7fa02f3/?me_id=1273157&item_id=21176555&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsupersportsxebio%2Fcabinet%2F1%2F7910301_64%2F8658863_m.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e636d5.b6083ef0.46e636d6.a723ee10/?me_id=1227000&item_id=10000803&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsuperfoot%2Fcabinet%2F08176980%2Fimgrc0120511365.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント