
ランニングシューズを短距離用で探している方にとって、自分の競技スタイルに合った一足を見つけることは、記録向上にもケガ予防にも直結します。この記事では、「ランニングシューズ 短距離」と検索している方に向けて、用途や競技レベルに応じたシューズの選び方をわかりやすく解説していきます。
まずは短距離と長距離の違いを明確にし、それぞれに求められるシューズの機能について整理します。そのうえで、「短距離 薄底」のメリットや注意点、練習と試合で履き分けるべき理由についても触れていきます。
また、「ランニングシューズは何キロくらい使えますか?」という疑問にも具体的に答えつつ、「陸上競技で禁止されているシューズは?」といったルール面の情報もカバーします。
中学生や高校生に向けた短距離シューズのおすすめモデルも紹介し、「中学生 陸上 短距離 シューズ おすすめ」「高校生 陸上 短距離 シューズ おすすめ」などの検索ニーズにも応えます。
さらには、ナイキの人気モデルを比較できる「nike おすすめ チャート」や、「一番人気なのは?」といったランキング的な情報、「ランニングシューズはどこで手に入りますか?」という購入場所に関する疑問にも対応します。
短距離競技に取り組むすべてのランナーが、自分に最適なシューズと出会えるよう、幅広い視点から徹底的に解説していきます。
- 短距離と長距離で異なるシューズの選び方
- 中学生・高校生向けのおすすめ短距離シューズ
- 薄底シューズの効果と注意点
- 使用距離や禁止シューズなどの基本知識
ランニングシューズ短距離用の選び方と基礎知識
- 短距離と長距離の違いを知ろう
- 中学生におすすめの短距離用シューズ
- 高校生におすすめの短距離用シューズ
- 短距離ランニングには薄底が最適?
- ランニングシューズは何キロくらい使えますか?
- 陸上競技で禁止されているシューズは?
短距離と長距離の違いを知ろう

短距離と長距離では、求められる身体の使い方や走り方が大きく異なります。それにともなって、適したランニングシューズの構造や性能もまったく異なるものになります。自分の競技スタイルに合ったシューズを選ぶためにも、それぞれの特徴を正しく理解することが大切です。
まず、短距離走は100m~400m程度の距離を一気に駆け抜ける競技であり、爆発的な加速力と瞬発力が非常に重要になります。この種目ではスタートの反応や、加速時の力強い蹴り出しが勝敗を左右します。
こうしたパフォーマンスを支えるために、短距離用シューズはとにかく軽量であることが求められます。また、地面をしっかりと捉える優れたグリップ力や、力を効率的に伝える高反発素材が使用されている点も特徴です。
ソールも薄くて硬めに設計されており、無駄なエネルギー消費を最小限に抑えられるよう工夫されています。
一方、長距離走は5000mや10000mといった持久力が問われる種目です。長時間にわたり安定したフォームを保つことが重要となるため、着地時の衝撃吸収性や足全体のサポート力が求められます。
そのため、長距離用のシューズはクッション性が高く、足をやさしく包み込むような柔らかめのソールが使用されていることが一般的です。
重量も多少増しますが、その分足の負担を軽減し、レース終盤まで快適に走れるように配慮されています。
このように、短距離用シューズはスピードと加速を最大限に引き出すための仕様となっており、長距離用シューズは安定性と持久力をサポートするための設計になっています。つまり、競技距離によってシューズの選び方が大きく変わってくるため、用途に合わせたモデル選びが非常に重要になります。
中学生におすすめの短距離用シューズ

中学生が短距離走に取り組む際は、足の成長を考慮しながら、安全性とパフォーマンスを両立できるランニングシューズを選ぶことが重要です。特に、身体が発育途中である中学生にとって、過度に薄くて硬いスパイクタイプのシューズは避けた方が無難です。
まだ骨や関節が完全に成長しきっていない段階では、足への衝撃が過度になることで、ケガや故障につながる可能性があります。そのため、適度なクッション性を持ちながらも、軽量で柔軟性のある素材を使用したシューズが適しています。
これにより、安全かつ効果的に力を地面へ伝えることができ、フォーム作りの段階でも安定した走りが可能になります。
具体的には、アシックスの「SPブレード」シリーズや、ミズノの「クロノインクス」などのエントリーモデルが人気です。
これらのシューズはスパイクプレートが柔らかめに設計されており、足へのダメージを最小限に抑えながらも十分な反発力を発揮します。さらに、これらのモデルは部活動や学校の大会での実績も多く、信頼性の高いアイテムとして支持されています。
また、中学生は成長により足のサイズが頻繁に変化するため、数年単位で長く使える高価なモデルを選ぶよりも、買い替えしやすい価格帯のシューズを選ぶことが現実的です。必要に応じて定期的にフィッティングを見直すことも、快適に競技を続けるうえで欠かせません。
このように、中学生が短距離用シューズを選ぶ際には、成長段階の足に配慮した構造であるか、安全性と機能性が両立しているか、そして保護者にもやさしい価格帯かどうかといったポイントをバランスよく検討することが大切です。
適切なシューズを選ぶことで、より安心して競技に取り組むことができ、将来的なパフォーマンスの向上にもつながります。
高校生におすすめの短距離用シューズ

高校生になると、部活動や大会を通じて陸上競技に本格的に取り組む選手が増えてきます。この段階では、筋力や瞬発力、フォームなどが急激に発達するため、それに見合った高性能な短距離用シューズの選択が必要になります。
適切なシューズを選ぶことで、記録向上はもちろん、ケガのリスクも減らすことができます。
まず重視すべきは、シューズの反発力とグリップ性能です。短距離走ではスタートの爆発力と、その後の加速フェーズが結果に直結します。
したがって、足の力を効率良く地面に伝え、トラックをしっかりと捉えるアウトソールの設計が必要不可欠です。具体的には、スパイク付きまたはそれに近いグリップ構造があると、地面からの反発を得やすくなります。
次に、ミッドソールとプレートの硬さも重要な選定基準です。プレートが硬すぎると扱いが難しくなる場合がありますが、高校生であればある程度の剛性を持つシューズでもしっかり対応できる筋力と技術を持っています。
ナイキの「ズームスーパーフライエリート」やアディダスの「アディゼロ プライム SP2」などは、反発力と軽量性のバランスが優れており、全国大会レベルの選手からも高い支持を得ています。
加えて、足のフィット感も見逃せないポイントです。ラスト(足型)の形状が自分の足に合っていないと、パフォーマンスに悪影響を及ぼすだけでなく、靴擦れや疲労の蓄積にもつながります。足幅や甲の高さに合ったモデルを選ぶことで、長時間の練習にも対応しやすくなります。
また、耐久性とコストパフォーマンスも見ておきたい要素です。高校生は練習量も多く、シューズの消耗が早いため、性能だけでなく、ある程度の耐久性と手の届く価格帯のモデルを選ぶことが現実的です。用途に応じて練習用と試合用でシューズを使い分けるのも賢い選択です。
このように、高校生が短距離用シューズを選ぶ際は、反発力・グリップ力・足へのフィット感に加え、耐久性やコストまでを含めて総合的に判断することが求められます。最適な一足を見つけることで、さらなる記録更新に近づくことができるでしょう。
短距離ランニングには薄底が最適?

短距離ランニングにおいて、薄底シューズは非常に有効な選択肢の一つです。特にスプリントのような瞬発力が求められる場面では、地面との距離が近いことで接地感が高まり、素早い動きに対応しやすくなります。
これにより、走行時の反応速度が向上し、スタートからの加速がよりスムーズになる傾向があります。
薄底のシューズは、構造上クッションが少ない分、足裏から地面への力の伝達がダイレクトになります。この構造が、地面を強く蹴る必要のある短距離走において大きなメリットとなるのです。
また、シューズ自体の重量が軽いため、足の回転を妨げにくく、ピッチ走法との相性も良好です。
ただし、薄底がすべての選手にとってベストな選択肢とは限りません。特に筋力がまだ十分でない選手や、フォームが安定していない初心者にとっては、薄底特有の衝撃が足や関節に大きな負担をかける可能性があります。そのため、筋力やフォームの安定性に応じて選ぶ必要があります。
さらに、薄底の中にも多様なタイプがあり、競技用に特化したモデルもあれば、練習用にクッション性を持たせたモデルも存在します。たとえば、トラック競技に向けた薄底スパイクと、ロード練習用の薄底レーシングシューズでは設計が異なるため、使用シーンに合わせた使い分けが重要です。
このように、薄底シューズは短距離ランナーにとって多くの利点がありますが、自分の身体的特性や競技レベル、使用目的をしっかりと理解した上で選ぶことが重要です。適切に使いこなせば、スタートの加速や中盤のスピード維持に大きなアドバンテージを得ることができるでしょう。
ランニングシューズは何キロくらい使えますか?

ランニングシューズの使用可能な距離は、用途や構造、使用状況によって大きく異なります。一般的に、トレーニング用のシューズであれば500km〜700kmが目安とされています。一方で、短距離用やスパイクタイプのシューズは、使用できる距離がもっと短くなる傾向があります。
特に短距離向けのシューズは、軽量性と反発力を重視して作られているため、耐久性よりもパフォーマンスが優先されています。このような構造の影響で、使用回数が20回〜30回程度を超えると、プレートのしなりや反発力に変化が見られることがあり、スピードやフォームに影響を及ぼす可能性もあります。
さらに、練習環境によっても消耗度は変わります。たとえば、舗装路での練習が多い場合や、悪天候下での使用が続くと、アウトソールの摩耗が進みやすくなります。同じ距離でも、走行する地面の硬さや傾斜によって劣化スピードが変わるのです。
このような点から、キロ数だけで判断せず、シューズの状態をこまめにチェックすることが大切です。アウトソールのすり減り、アッパーの破れ、フィット感の低下などが見られる場合は、たとえ走行距離が少なくても交換を検討しましょう。
また、試合用と練習用でシューズを使い分けることで、それぞれの寿命を伸ばすことができます。競技会では最大限の性能を発揮できるよう、温存しておくのも一つの工夫です。
陸上競技で禁止されているシューズは?

陸上競技では、特定の基準を超えるシューズの使用が禁止されています。これは競技の公平性を保つためであり、世界陸上競技連盟(ワールドアスレティックス)が公式にルールを定めています。
例えば、短距離種目におけるシューズのソール厚は「20mm以下」と規定されています。これは、厚底シューズにより得られる過剰な推進力が、他の選手との間に不公平な差を生む可能性があると判断されているためです。実際、一部の厚底スパイクは規定違反として公式大会では使用できなくなっています。
さらに、ソールの中に挿入されているプレートの素材や構造にも制限があります。カーボンファイバーなどの強化素材を使用したプレートが一般的ですが、過剰な反発性や屈曲性を持つ設計は許可されていません。製品によっては見た目ではわからない違反もあるため、購入時に最新のルールに対応しているか確認することが重要です。
また、まだ市販されていない試作品や限定モデルなど、正式販売から4ヶ月以上経過していないシューズは、大会で使用することができません。この制限は特定選手だけが新技術を先に使える事態を避けるために設けられています。
もっとも、これらのルールは主に国際大会や公認記録が関係する競技に適用されるため、部活動の練習や記録会などでは柔軟に対応される場合もあります。それでも、高校生や中学生が大会に出場する際には、所属する指導者や大会要項で使用可能なシューズを事前に確認しておくべきでしょう。
このように、性能だけでなくルールの適合性にも目を向けてシューズを選ぶことが、安全で公正な競技参加につながります。
ランニングシューズ短距離用の人気モデルと選び方

- 一番人気なのはどのモデル?
- nikeおすすめチャートで選ぶモデル比較
- ランニングシューズはどこで手に入りますか?
- 短距離用でもクッション性は必要?
- 練習と試合で履き分けるべきシューズ
一番人気なのはどのモデル?

短距離用のランニングシューズにおいて、近年もっとも注目を集めているモデルの一つが、ナイキの「ズームスーパーフライエリート2」です。このシューズは、世界大会や全国レベルの競技会でも使用されており、トップアスリートの多くが選んでいることから、その性能の高さがうかがえます。競技での実績はもちろん、機能性とデザイン性の両立も人気の理由となっています。
最大の特長は、軽量でありながら優れた反発力を持つ点です。足裏のエネルギーを推進力に変えるフルレングスのカーボンプレートが内蔵されており、スタートダッシュから加速、トップスピードの維持まで一貫してサポートしてくれます。また、トラックとの接地時間を最小限に抑える設計がなされており、より高い走行効率が得られます。
さらに、アッパーには通気性の高いニット素材が使われ、長時間の着用でもムレにくく、フィット感も非常に良好です。シューズの構造も極限まで無駄を削ぎ落としたミニマルな設計となっており、まるで自分の足と一体化しているような感覚が得られるのも魅力です。
ただし、価格帯は比較的高めであり、スパイク特有の履き心地に慣れていない選手にとっては使いこなすまでに時間がかかることもあります。こうした理由から、初心者や中級者には、よりクッション性や安定感のあるモデルを選ぶほうが適している場面もあるでしょう。ナイキであれば「ズームライバルスパイク」などがその代表例で、コストパフォーマンスに優れ、多くの学生アスリートに支持されています。
このように、人気モデルには理由があり、自身の競技レベルや用途に応じて適切に選ぶことで、そのポテンシャルを最大限に発揮できます。一番人気のモデルに飛びつくのではなく、自分に合った一足を見極める視点を持つことが、シューズ選びで失敗しないためのコツと言えるでしょう。
nikeおすすめチャートで選ぶモデル比較
ナイキの短距離用ランニングシューズには、多種多様なモデルが用意されており、使用者のレベルや目的によって適切な選択が必要です。各モデルには明確な特徴があり、自分に合ったシューズを選ぶことで、走行パフォーマンスは格段に向上します。ここでは、ナイキのおすすめモデルをチャート形式で比較し、それぞれの特長を詳しく解説していきます。
| 使用レベル | モデル名 | 特徴 |
|---|---|---|
| 初心者 | ズームライバルスパイク | 手頃な価格、足にやさしいクッション性、適度なグリップと安定感を備える入門向けモデル |
| 中級者 | エアズームマックスフライ | 高反発とクッション性のバランスが良く、フォームの改善にもつながる設計 |
| 上級者 | ズームスーパーフライエリート2 | 超軽量、高反発構造、トップレベルの競技者向けに設計されたハイパフォーマンスモデル |
| 練習用 | ペガサスターボ | クッション性に優れ、長時間のトレーニングやリカバリーランに最適 |
| 試合用 | ドラゴンフライ | ピン付きで爆発的な加速力を発揮、トラック競技に特化した設計 |
このようなチャートを参考にすることで、自分の競技スタイルやトレーニング状況に合った一足を選びやすくなります。たとえば、初めてスパイクを購入する中学生であれば「ズームライバルスパイク」、全国大会を目指す高校生であれば「エアズームマックスフライ」や「ズームスーパーフライエリート2」が候補になるでしょう。
また、試合用と練習用を分けて使用することも、シューズの寿命を延ばしつつ、それぞれの特性を最大限に活かす手段となります。練習ではクッション性と耐久性を重視し、試合では軽量性と爆発的な推進力を求める、というように使い分けることが重要です。
ナイキのランニングシューズは、常に最新のテクノロジーを取り入れており、競技レベルを問わず幅広い選手に対応できるラインナップが揃っています。どれだけ高性能なシューズでも、自分の足に合わなければその効果は半減してしまいます。
できる限り専門店での試し履きを行い、フィット感や履き心地を確かめてから選ぶようにしましょう。そうすることで、自分にとっての“最高の一足”に出会える可能性が高まります。
ランニングシューズはどこで手に入りますか?

短距離用のランニングシューズは、専門性が高いため購入場所の選定が重要です。主な購入先としては、スポーツ用品店、メーカーの公式オンラインショップ、陸上競技専門店、そして大手ECサイトが挙げられます。それぞれの特徴を理解して選ぶことで、より自分に合った一足を見つけることができます。
スポーツ用品店では、実際に試し履きができる点が大きなメリットです。特にフィット感が重要な短距離用シューズでは、サイズ感や履き心地をその場で確かめられることが大きな安心材料になります。また、店員に相談すれば、自分のレベルや使用目的に応じたモデルを提案してもらえることもあります。
一方、メーカーの公式サイトやECサイトでは、最新モデルの在庫が豊富で、限定カラーやキャンペーンなどに出会えるチャンスもあります。近くに店舗がない人や、忙しくて足を運べない人には便利な選択肢です。
ただし、サイズ選びには注意が必要なので、レビューやサイズチャートをしっかり確認して購入するのが望ましいでしょう。
さらに、陸上競技専門店では、競技に特化したアドバイスを受けられるのが魅力です。大会仕様のモデルや、選手向けの限定品など、一般の店舗では手に入りにくいシューズを取り扱っている場合もあります。
こうした店舗では、競技経験のあるスタッフから実践的なアドバイスがもらえることも多く、特に学生アスリートには心強い味方になるでしょう。
このように、購入場所によって得られる情報やサービスは異なります。自分の目的やライフスタイルに合わせて、最適な購入ルートを選ぶことが大切です。
短距離用でもクッション性は必要?

短距離用のランニングシューズにおいても、クッション性は決して無視できない要素です。多くの人は「短距離=薄底=クッション不要」と思いがちですが、それは試合や競技場での使用に限った話であり、日々の練習やウォーミングアップでは状況が異なります。
短距離走では瞬発力と加速力が求められるため、レース用シューズは極限まで軽量化されており、地面からの反発を効率よく活かす構造が取られています。
そのため、クッション性は抑えられがちです。しかし、これを日常のトレーニングにそのまま使うと、足裏や膝、腰への負担が蓄積されやすくなり、長期的にはケガや慢性的な痛みにつながる恐れがあります。
そのため、練習用には適度なクッション性を持つモデルの使用が推奨されます。たとえば、ミッドソールにやわらかさを持たせたシューズであれば、足への衝撃を和らげつつ、必要な反発力も確保できます。
また、クッション性があることでフォームの安定性も向上し、無理のないトレーニングが可能になります。
さらに、成長期にある中学生や高校生は、身体の発達途中にあるため、過度な衝撃は成長障害のリスクを高めることもあります。このような年代では、たとえ短距離用であっても、衝撃吸収に配慮したモデルを選ぶのが安心です。
このように、短距離用のシューズでもクッション性のあるモデルを選ぶ場面は多くあります。目的に応じて使い分けることが、長く安全に競技を続けるための基本といえるでしょう。
練習と試合で履き分けるべきシューズ

ランニングシューズを練習用と試合用で分けることは、多くの競技者が実践している基本的なシューズ戦略です。この履き分けには、シューズの性能を最大限に活かすとともに、ケガのリスクを減らすという2つの大きな利点があります。
練習用シューズは、長時間の使用に耐えられる耐久性や、足への負担を軽減するクッション性が重視されます。たとえば、毎日のスプリント練習やフォーム確認に使うシューズは、やや厚底でクッション性の高いモデルを選ぶことで、関節や筋肉へのダメージを抑えながらトレーニングを継続することができます。
また、安定性の高い設計のものは、フォームの乱れやケガのリスクを減らす点でも有効です。
対して試合用のシューズは、軽量化と反発力に特化した設計となっており、瞬発力やスピードを重視する仕様です。スパイクピン付きのモデルや、カーボンプレートを内蔵した高反発素材のシューズは、レース中のパフォーマンスを最大限に引き出します。
ただし、こうしたシューズは構造が繊細であり、長時間の使用には向いていません。練習で使い続けると性能が劣化しやすくなるため、寿命を縮める要因になります。
また、履き分けることで心理的な切り替えにも効果があります。練習と試合でシューズを変えることで、「今日は本番だ」という意識づけが自然と生まれ、集中力の向上にもつながるのです。
このように、目的に応じてシューズを使い分けることは、競技力の向上だけでなく、身体のケアやメンタル面にも大きく影響します。パフォーマンスを追求する競技者ほど、日々の履き分けを徹底しているのです。
ランニングシューズ短距離用の選び方と活用ポイントまとめ
- 短距離と長距離ではシューズの設計思想が根本的に異なる
- 短距離用は軽量かつ高反発で加速性能を重視する
- 長距離用はクッション性と安定性を重視して設計されている
- 中学生は足の成長を考慮し、柔らかめのプレート構造が安全
- 高校生は筋力と技術に応じて本格的な反発性モデルが選択肢となる
- 薄底シューズは加速に優れるが、選手の筋力に応じて慎重に選ぶべき
- 使用距離の目安は500km~700km、スパイクはもっと短い
- シューズの寿命は走行距離だけでなく状態確認が重要
- ソールの厚みやプレート素材によって大会で使用できない場合がある
- 一番人気はナイキのズームスーパーフライエリート2
- ナイキのモデルは用途別に明確な使い分けが可能
- 練習用と試合用でシューズを履き分けるのが理想
- 練習ではクッション性と耐久性を優先すべき
- 試合では軽量かつ高反発なモデルで最大限のパフォーマンスを引き出す
- シューズはスポーツ店・専門店・オンラインなどで用途に応じて購入するのが望ましい
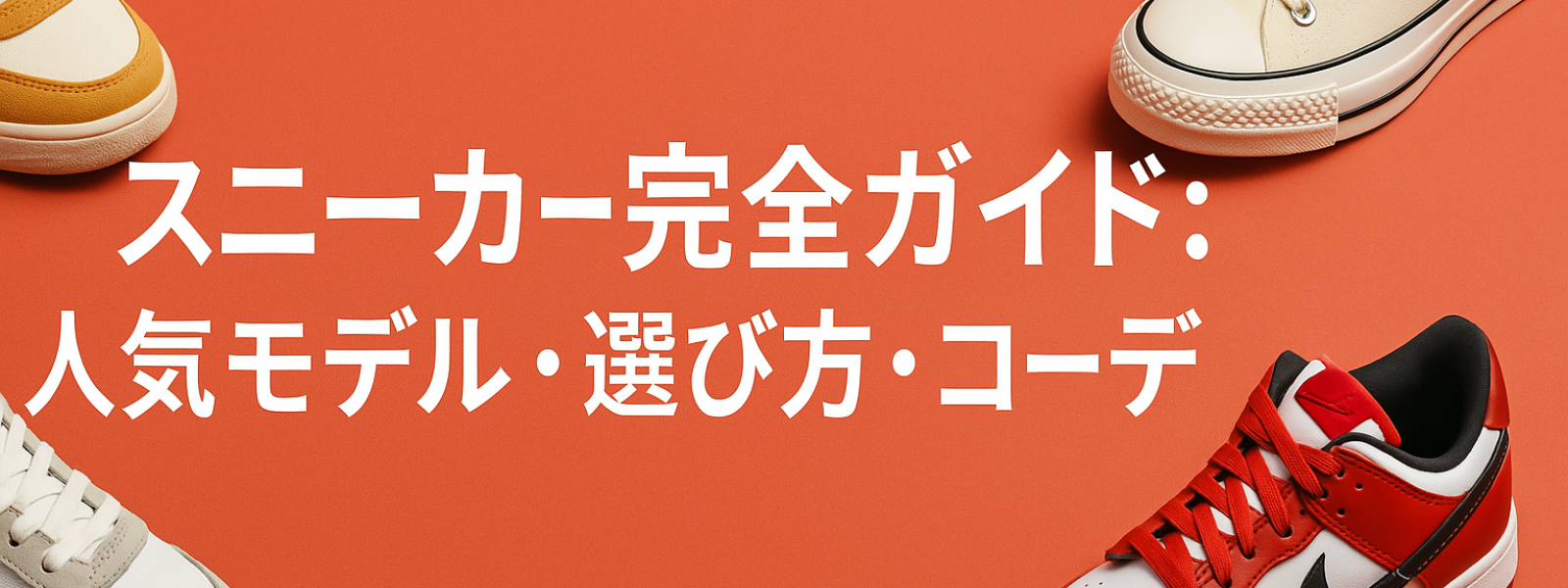
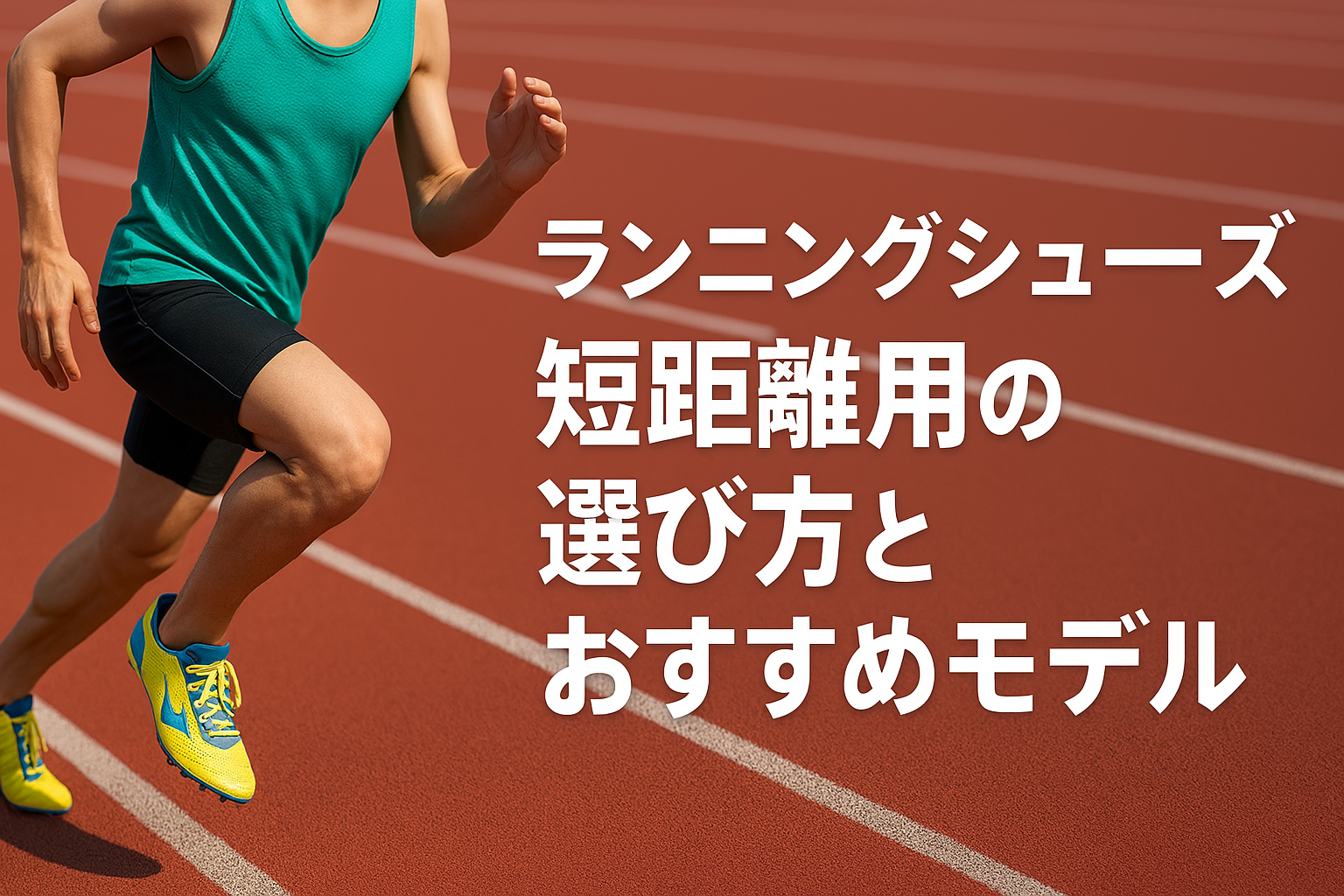
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/470236fa.751f7246.470236fb.754bd8c8/?me_id=1213746&item_id=10131928&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsamsam%2Fcabinet%2Ftf_running%2Ftf_spike%2F1093a2401.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/470237a8.08315b87.470237a9.5badc526/?me_id=1250049&item_id=10030058&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fabespo%2Fcabinet%2F11299305%2Fimgrc0094665808.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47023a10.db50b37b.47023a11.f7360fb1/?me_id=1387100&item_id=10042452&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkicksparrow%2Fcabinet%2Ftool_images_top_70%2Fu4041759_01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4702422d.7cbdf611.4702422e.3efa6389/?me_id=1269994&item_id=42530105&pc=https%3A%2F%2Faffiliate.rakuten.co.jp%2Fimg%2Fdefault_image.gif)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e62921.d767bc9f.46e62922.ded9a904/?me_id=1195055&item_id=10233098&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsportsmario2%2Fcabinet%2Fevidence_20250227%2Fi02hl309707_1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47024b8c.cd923337.47024b8d.32be9608/?me_id=1362789&item_id=10072927&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffrenz2%2Fcabinet%2Ftool_images_top_94%2Ft4031146_01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47024d1f.374fd3da.47024d20.9501512d/?me_id=1315051&item_id=10058037&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsposaku%2Fcabinet%2Fclossmall77%2Ffv6040-800-00.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47024d1f.374fd3da.47024d20.9501512d/?me_id=1315051&item_id=10057953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsposaku%2Fcabinet%2Fclossmall76%2Ffv6040-101-00.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/470241af.4caff41f.470241b0.b0700885/?me_id=1388734&item_id=10025999&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fraise-sneaker%2Fcabinet%2F10176998%2Ffd8396-900_0.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4702422d.7cbdf611.4702422e.3efa6389/?me_id=1269994&item_id=42967109&pc=https%3A%2F%2Faffiliate.rakuten.co.jp%2Fimg%2Fdefault_image.gif)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46affe48.58e1358c.46affe49.63b20d5f/?me_id=1389886&item_id=10015505&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnike-official%2Fcabinet%2F20240620fa%2Fdc3728-101_a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46affe48.58e1358c.46affe49.63b20d5f/?me_id=1389886&item_id=10015285&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnike-official%2Fcabinet%2F20240603fa%2Fdd0204-003_a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47025829.78c0dfb2.4702582a.42a11f4d/?me_id=1268947&item_id=10213390&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fadidas%2Fcabinet%2Fp60%2Fjs0493_l.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47025973.6bcf90f0.47025974.b8b7fab4/?me_id=1371798&item_id=10016178&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Funderarmour%2Fcabinet%2F009%2Fu30287510001_1001.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント